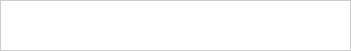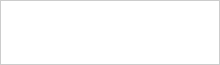農村をはじめ全国各地の神社では、春には農作物の豊作を祈願し、秋には稔りに感謝するお祭りが行われてきました。これらのお祭りは、神社の神事の中でも特に重要なものとして位置づけられています。
「農」は私たちに食べ物をもたらし、安定した暮らしの基礎といえます。かつて凶作は、人々の生命をも奪う一大事でした。飽食の時代といわれる今日にあっても、世界を見渡すと決して過去のこととはなっていません。また、食料の確保が安定すると、知識や技術が高度化し産業が興り、文化・芸術が育まれるなど、人々の暮らしが豊かになっていきます。
古代から食料を確保することが、集落や国家の重要な役割の一つでした。地域を治めた領主たちは、地域の安寧と繁栄のために豊作を願い感謝する神事、いわゆる「まつり」を行ってきました。政治を「まつりごと」というのは、一つにはこうした理由からと言われています。
天皇陛下は、皇居の神殿で、祖先の神々たちに感謝し世の中の平和と繁栄を願って、日々まつりを続けておられます。
日本人はこれまで、神々へ詣でること、神をまつることで、私たちを育む万物へ、そして働く人たちへの感謝の気持ちを表してきました。また、古くから伝わる伝統行事や文化の中には、神事に由来するものがたくさん伝えられています。
現代社会において、私たちは、感謝の気持ちを具体的に表現す機会が少なくなってきました。
いわば神をまつることは、日本らしい心の表現方法の一つであり、瑞穂の国の原点として、今もとても大切なものだと感じます。